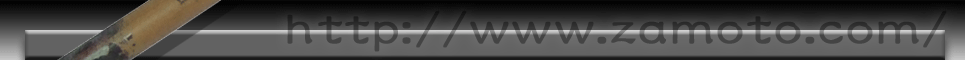「連綿行書体の制作ポイント」解説会
平成21年3月13日より15日まで、「連綿の美を求めて」というテーマで、太源書道会選抜展が開催されました。太源書道会では、日頃、古典臨書を中心に勉強を重ね、近代詩、漢字作品制作が行われているようです。
3月15日は、嚶嚶・座本大汪による「連綿体・制作のポイント」と題する解説会・揮毫会を行い、太源会員の方を始め、他会派からも多数参集頂きました。
解説会は、太源副理事長・向井三聖先生の進行、理事長・北野摂山先生による質疑という形で始まりました。まず、質疑応答の様子です。
- 北野先生
- 私たちは、中長鋒の羊毛さばき筆を使うが、何を使われますか?
- 座本大汪
- 件毫のむじな毛・いたち毛あるいはそれらに多少羊毛を巻いた筆を主に使っています。又、作品書き等には、羊毛筆も使います。件毫は腰が強く速い動きに対応でき、強い線(シャープ)が出せるからです。
- 北野先生
- 紙は、中国のアモイ宣や紅星牌が紙にくっつくようなものを使うが、どんな紙を使いますか?
- 座本大汪
- 一番使うのは、高麗宣です。中国の単宣等も使い書作します。
- 北野先生
- 墨は、ほとんど濃墨を使うが・・・・・
- 座本大汪
- 固形墨を磨る。濃さは中濃ぐらいである。
という、分房四宝について答えてくださいました。更に、
- 北野先生
- 連綿作品は行書を中心とした作品が多いが何故でしょうか?
- 座本大汪
- 行書は無理なく書けるということで、行書を中心に草書を配分した作品になる。
- 北野先生
- 連綿を身につける素養は?
- 座本大汪
- 私たちは、宋の米芾・黄庭堅をはじめ、明清の王鐸や陳淳、祝允明などを臨書してきた。
- 北野先生
- 最後に「連綿体制作のポイント」を教えて下さい。
- 座本大汪
- (半切作品を示しながら)
「へん」と「つくり」による粗密の変化をつけること、
一行目を書き二行目を考えること、
上の文字を授け、作品の骨を作ること、
懸針(縦に引く画を強調)も連綿空間処理の一つであること、
一つの文字を一つと捉えず、二字・三字先も考えること、等である。
以上、途中省略していますが、30分ほど話をさせて頂きました。
その後、揮毫会を行い、半切1/2に二字・三字、そして半切二行を説明を加えながら、揮毫致しました。
揮毫会が一旦終了した後も、使用した筆を見るためや質問をして頂いたり座本大汪にとっても楽しく貴重なひとときとなりました。
北野先生・向井先生並びに太源書道会員のみなさま、誠に有難うございました。